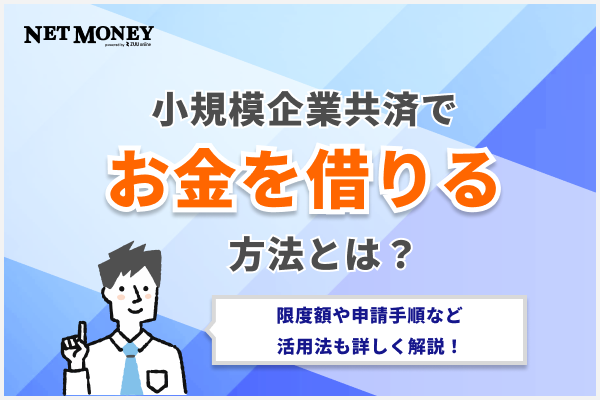
個人事業主の方で、資金繰りに悩んだ経験はありませんか? 事業の継続には資金調達が不可欠ですが、状況によっては金融機関からの融資を受けるのが難しい場合もあるでしょう。
そんな時、小規模企業共済の貸付制度が助けになるかもしれません。なぜなら、この制度は積み立てた掛金を担保に、最大2,000万円まで事業資金を借り入れることができるからです。
本記事では、小規模企業共済でお金を借りる方法を詳しく紹介します。また限度額や申込方法についても解説するので、小規模企業共済の貸付制度を検討している方は参考にしてください。
小規模企業共済の貸付制度は毎月の掛金からお金を借りられる制度
小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主や会社役員のための退職金制度です。事業主が毎月一定額の掛金を積み立てて、将来の生活の安定や事業の再建に備えるものです。
しかし、小規模企業共済の魅力は退職金制度だけではありません。小規模企業共済の貸付制度を利用することで、事業資金や緊急時の資金調達も可能となります。
ここで、小規模企業共済の貸付制度について詳しく解説します。
積み立てた掛金を担保にお金を借りられる
小規模企業共済の貸付制度は、加入者が積み立てた掛金を担保として、低金利でお金を借りられる仕組みです。
通常の銀行融資とは異なり、事業の業績や個人の信用力に関係なく、積立金の範囲内で融資を受けられることが大きな特徴です。
日々の事業運営で資金が必要になった場合や、予期せぬ出費に直面した際、自分が積み立てた掛金を活用して資金を調達できます。万が一の備えとして、小規模事業者にとって心強い味方となるでしょう。
即日融資可能!一般貸付で最大2,000万円の事業資金を借りられる
小規模企業共済の貸付制度では、即日融資が可能なことも大きな特徴です。それだけでなく、高額の事業資金も借りられます。
一般貸付の場合、最大で2,000万円まで借入れが可能です。
事業経営においては、急な設備投資が必要になった場合や、大型の受注に対応するための運転資金が必要になった場合など、即座に高額の資金が必要となるシーンは少なくありません。
小規模企業共済の貸付制度を利用すれば、万が一の非常事態にも、迅速かつ柔軟に資金調達を行えます。
審査なし!他社から借入れあっても融資を受けられる
小規模企業共済の貸付制度は、審査なしで、他社から借入れがあっても融資を受けられます。一般的なローンとは異なり、自身が積み立ててきた掛け金からお金を受け取るためです。
また、他社からの借入れがある場合でも、小規模企業共済の貸付制度を利用できます。 一般的な金融機関の融資では、他社からの借入れがあると審査に通りにくくなる場合があります。しかし、小規模企業共済の貸付制度は、掛け金を担保としているため、他社からの借入れ状況は審査に影響しません。
そのため、書類を準備して審査を通す必要がないので、すぐに手元にまとまったお金を用意したい方におすすめです。
借入用途は事業資金・生活費など幅広い
小規模企業共済の貸付制度は、幅広い借入用途に対応できる点も特徴の一つです。事業資金や運転資金はもちろんのこと、緊急時の生活費まで、さまざまなニーズに対応できます。
例えば、事業の拡大に必要な設備投資資金や、日々の経営に必要な運転資金として活用できます。また、急な売上の減少や取引先の倒産など、不測の事態による資金繰りの悪化に対応するための緊急資金としても利用可能です。
さらに、経営者の病気や家族の介護など、個人的な事情で資金が必要になった場合でも、生活費の補填として借り入れることができます。
小規模企業共済の貸付制度は、事業資金だけでなく、生活費まで幅広い用途に利用できるため、経営者にとって非常に心強い存在と言えるでしょう。
小規模企業共済の貸付制度で借入れする条件
小規模企業共済の貸付制度を利用するにはいくつかの条件を満たす必要があります。ここでは、小規模企業共済の貸付制度を利用するための以下3つの条件について解説します。
共済加入資格は従業員が一定以下いる個人事業主または会社の役員
小規模企業共済への加入資格は、小規模事業で働く経営者や役員、従業員が一定以下いる個人事業主であることです。共済に加入することで、掛金の所得控除や事業資金の借入が可能になります。
正社員をはじめとした法人での雇用関係にあたる方は、小規模企業共済に加入できないので注意してください。
12カ月以上の掛金積立が利用条件
貸付制度を利用するには、小規模企業共済において最低12カ月以上の掛金積立が必須です。
また、借入れの最低額は10万円からとなっており、5万円単位での借入れとなっています。そのため、加入後すぐの利用は難しいので注意しましょう。
ある程度の掛金積立がなされた後に、初めて融資を受けられるようになっています。
借入可能額は積立金の最大7~9割
貸付制度では、借入可能額は加入者自身の掛金総額に基づいて決定されます。これは、加入者自身の積立金を担保として借入れを行うためです。
借入額は契約者の掛金状況によって異なりますが、積立金の最大7割~9割までの借入が可能です。長期間にわたって多くの掛金を積み立てている加入者ほど、より多くの借入れができます。
小規模企業共済の貸付制度の申込方法手順
小規模企業共済の貸付制度は、ほかの融資制度と比較して手続きがスムーズなことも特徴です。ここでは、小規模企業共済の貸付制度の利用手順について解説します。
申請書類は中小機構のウェブサイトまたは支部窓口から取得
小規模企業共済の貸付制度の申請を行う際、まず必要なのは申請書類の準備です。申請書類は、中小企業基盤整備機構(中小機構)のウェブサイトからダウンロードするか、各支部窓口で直接入手できます。
中小機構のウェブサイトでは、各種申請書類がPDF形式で提供されており、24時間いつでもアクセス可能です。
一方、中小機構の支部窓口では、担当職員に相談しながら書類を入手できるため、申請内容について不明な点がある場合には直接問い合わせるのがおすすめです。
申請時には掛金証明書や事業関連書類が必要
申請の際には、掛金証明書や事業関連書類が必要も準備する必要があります。
- 共済契約者の印鑑証明書
- 共済契約者の実印
- 身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
- 借入金額に応じた収入印紙
- 共済契約者番号と氏名が掲載されている中小機構からの送付物
小規模企業共済の貸付制度は自分で積み立てた掛金からお金を借りる仕組みであるため、特に審査はありません。申請後、最短で即日の貸付が可能です。
小規模企業共済の貸付制度を利用するメリット
小規模企業共済の貸付制度は、急な資金需要に対応できるだけでなく、いくつかのメリットがあります。
例えば、低金利で利用できる点や、担保や保証人が不要である点が挙げられます。ここでは、小規模企業共済の貸付制度を利用するメリットについて詳しく解説します。
低金利(0.9%または1.5%)で利用できるため返済負担が少ない
小規模企業共済の貸付制度では、低金利でお金を借りられることが大きなメリットです。
一般貸付では年利1.5%、特別貸付では年利0.9%で借入が可能です。返済時の負担が少なく、利用しやすい点が魅力です。
| 一般貸付 | 特別貸付 | |
|---|---|---|
| 金利 (実質年率) |
1.5% | 0.9% |
| 概要 | もしものときに、迅速に事業資金等を借入れできる | 特別な事情がある場合に限り借入れできる (緊急経営安定貸付、傷病災害時貸付け、福祉対応貸付など) |
保証人や担保なしで借りられる
小規模企業共済の貸付制度は、今までに積み立ててきたお金を借りるため、保証人や担保を立てる必要がありません。共済金からまとまったお金をすぐ手元に準備できるので、緊急でお金が必要になった場面に役立ちます。
小規模企業共済の貸付制度のデメリット
小規模企業共済の貸付制度にはデメリットもあります。例えば、貸付制度の利用には一定の条件を満たす必要があります。また条件によっては借入限度額が少なくなる場合があります。具体的に、以下2つのデメリットを見ていきましょう。
1年以上掛金納付がないとお金を借りられない
小規模企業共済の貸付制度のデメリットは、1年以上掛金納付がないとお金を借りられないことです。小規模企業共済は、事前に積み立てたお金から借入する制度のため、1年以上掛金納付が条件になります。そのため、共済に加入して1年分の掛金納付をおこなっていない状態では、貸付制度を利用できません。
掛金が少ない場合は借入れできる金額が限定的
小規模企業共済の貸付制度は、掛金が少ない場合には借入れできる金額が限定的であるというデメリットがあります。この貸付制度は、最大で積立金の7割~9割までの借入れとなるため、掛金の積立額が少ない場合は希望する額を借りられません。
例えば、毎月の掛金が1万円の場合、積立額が少ないため、借りられる金額も限られてしまいます。
したがって、小規模企業共済の貸付制度を利用する際は、将来的な借入希望額も見据えて、掛金を検討することが重要です。
小規模企業共済の貸付制度でいくら借りられる?実際にシミュレーションした
小規模企業共済の貸付制度ではいくら借りられるのでしょうか。実際にシミュレーションをして借入額を算出してみましょう。
ここでは、毎月支払っている掛金を1万円、3万円と仮定した場合、どれくらいの金額を借入できるのかを解説します。
毎月掛金1万円の場合
小規模企業共済に毎月1万円支払っている場合、貸付限度額は以下のようになります。
| 掛金納付期間 | 積立総額 | 貸付限度額 |
|---|---|---|
| 1年 | 120,000円 | 84,000~108,000円 |
| 2年 | 240,000円 | 168,000~216,000円 |
| 3年 | 360,000円 | 129,600~324,000円 |
| 4年 | 480,000円 | 336,000~432,000円 |
| 5年 | 600,000円 | 420,000~540,000円 |
小規模企業共済の貸付制度は、積立金の額に応じて借入限度額が決まる仕組みであるため、掛金納付期間が長くなればなるほど高額を借りられます。
毎月掛金3万円の場合
小規模企業共済に毎月3万円支払っている場合、貸付限度額は以下のようになります。
| 掛金納付期間 | 積立総額 | 貸付限度額 |
|---|---|---|
| 1年 | 360,000円 | 252,000~324,000円 |
| 2年 | 730,000円 | 504,000~648,000円 |
| 3年 | 1,080,000円 | 756,000~972,000円 |
| 4年 | 1,440,000円 | 1,008,000~1,296,000円 |
| 5年 | 1,800,000円 | 1,260,000~1,620,000円 |
毎月3万円を積み立てると借入金額が高額になりますが、高額を借り入れると利息も高くなるので綿密な返済計画を縦から借入れしましょう。
小規模企業共済の貸付制度を利用する際の注意点
小規模企業共済の貸付制度は資金調達にとても便利ですが、利用の際はいくつかの注意点があります。具体的に、以下3つの注意点を押さえておきましょう。
積立金の範囲内でしか借入できないため過剰な借入はできない
小規模企業共済の貸付制度では、担保が掛金の総額に限定されています。そのため、積立金の範囲内でしか借入ができません。つまり、掛金以上の借入は不可能です。
過剰な借入を防ぐ仕組みである一方、多額の資金調達には対応できない可能性もあるため、他の融資制度との使い分けが必要となります。
借入金は解約時に相殺される可能性がある
借入金は解約時に相殺される可能性がある点にも注意が必要です。
例えば、解約時に未返済の借入金がある場合、掛金と利子分の金額が解約手当金から差し引かれることになります。
将来受け取る予定だった退職金が減少してしまう可能性があるため注意しましょう。
返済が遅延すると信用情報に悪影響が出る可能性がある
貸付金の返済が遅延したり、滞納が続いたりすると、新たな借入ができなくなるだけでなく、信用情報に悪影響が出る可能性があります。
将来的な融資利用に支障をきたす可能性があるため、返済計画は慎重に立てることが重要です。
また、返済が遅延した場合は返済日の翌日から入金があった日までの期間につき、返済が遅れた元金に対して年14.0%の損害金を支払わなければなりません。
小規模企業共済貸付の代替手段と比較
小規模企業共済貸付のほかにも、緊急小口資金貸付や消費者金融、掛金の現金化などの資金調達方法があります。小規模企業共済貸付との違いや比較ポイントについて、それぞれ解説していきます。
緊急小口資金貸付は無利息で利用可能
小規模企業共済を利用できない場合、緊急小口資金貸付の利用を検討するのもひとつです。緊急小口資金貸付は、一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用を借入れできる制度です。
小規模企業共済貸付では利息が発生しますが、緊急小口資金貸付は無利息で利用できるのが大きな特徴です。貸付上限は少額ですが、保証人不要で借りられます。
消費者金融や銀行ローンと比べた際の優位性
小規模企業共済の貸付制度は、消費者金融や銀行のカードローンと比較して年利0.9%~1.5%という金利の低さが魅力です。また、審査不要なので事業者にとって申込のハードルも低く、最短即日で融資を受けられることもメリットです。
掛金を解約して現金化する選択肢もある
小規模企業共済の掛金を解約し、一括で現金を受け取るという選択肢もあります。これにより、急な資金需要が生じた際などに、掛金を活用して資金を調達できます。
具体的には、掛金を解約することで、それまで積み立ててきた金額に応じた解約手当金を受け取ります。
ただし、この方法を選ぶ際は解約控除に注意が必要です。特に加入期間が20年未満の場合、受け取る金額が掛金総額を下回る可能性があるため、解約を検討する際には、将来受け取れるはずだった共済金との比較や、他の資金調達手段との比較を行い、慎重に検討するようにしましょう。
小規模企業共済でお金を借りる際に関するよくある質問(Q&A)
小規模企業共済でお金を借りる際、さまざまな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?ここでは、小規模企業共済でお金を借りる際によくある質問とその回答をまとめました。

