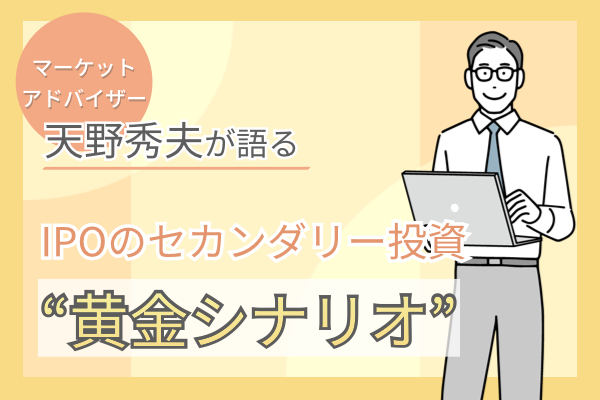
証券専門紙に入社した1987年当時はバブル経済が加速しはじめた頃。東証にはまだ立会場があって建て替え前。証券界は野村、大和、山一、日興の4社体制が組まれて、マザーズ市場はまだなく、ジャスダックは店頭市場と呼ばれていた。株式市場では「ウォーターフロント関連」という相場テーマが大いに盛り上がり、証券界はシナリオ営業が全開期だった。
しかし、当時から成長株という言葉は存在し、新規上場株も人気化したことは今でも変わらない。仕事の関係上、直接投資の経験などはないものの、30年以上、株式市場を眺めてきて銘柄の選別には独自の視点を持っている天野氏に銘柄選定の仕方などについて話を聞いた。
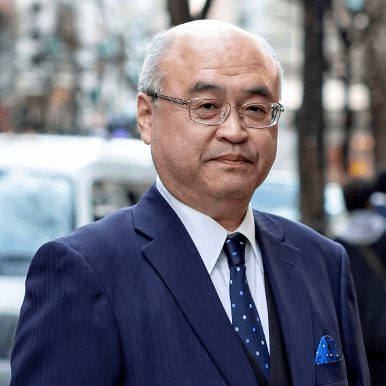
IPOセカンダリー投資はコツを知れは高勝率

今でこそ新規上場(IPO)の初値はブックビルディング方式(需要積み上げ方式)による価格決定方式が採用されているが、店頭市場の時代には、買い注文と売り注文とを一定時刻に一斉につきあわせて取引価格を決定する統一価格入札方式「ダッチ方式」が長らく行われていた。発行会社の社長など関係者と主幹事証券が顔を突き合わせて初値を決めていたのである。初値を決めるために幹事証券は「もっと売り物(冷やし玉)を出してほしい」、上場会社側は「いやまだ出さない、もっと初値は上だ」などと「丁々発止」の時代があったのだ。
このIPO人気は以前からあったわけだが、政府保有株の第1回目の売り出しによる1987年2月のNTTの新規上場で火が付き、現在のZホールディングス(4689)であるヤフーが1997年に公開価格70万円に対して初値200万円でIPOし、その後、1対4の株式分割を経て2000年のITバブル時に株価は1億円を突破した。とんでもない事態があったわけで、これがまさしくバブル現象といえる。その結果、IPOは儲かる、というIPO神話が生まれて、その人気化や効果には濃淡がありながらもIPOは個人投資家にとって注目度が高い投資テクニックになっていった。
テンバガーを秘めるIPO銘柄
とはいえ、公開価格でIPO株を得るには一般的に抽選で当たる必要があり、人気銘柄ほど競争倍率が高くなることからIPO投資を敬遠する個人投資家も少なくない。しかし、IPO銘柄の上場後に投資する「セカンダリー投資」も意外と高い勝率が見込まれる。
また、「IPOはテンバガーの近道」との持論を持つのが複眼経済塾の渡部清二代表取締役塾長。テンバガーのことを広め、『会社四季報』の研究でも第一人者である。その渡部塾長は、「IPOの公募で当たらなくても、株価流動性の高いIPO後の株価次第ではテンバガーとはいわなくても2倍、3倍のキャビタルゲインを得ることができるのがIPO投資だ」と解説する。もちろん、公開価格の数倍となった初値を買うのではなく、その後の落ち着いた株価局面で買うことが肝要だ。
IPOセカンダリーの黄金シナリオ
私が、IPO銘柄を店頭市場(現在のジャスダック)時代からみていて、IPOのセカンダリー投資で大きくキャピタルゲインが狙える「黄金シナリオ」がある。
それが、「IPO」→「初決算発表」→「株主還元」→「市場変更」のコースだ。
IPO時には事業内容、たとえばIT関連、AI関連ならば初値が高騰しやすくなるなど銘柄ごとに人気の濃淡は出やすい。そして、一般的にIPO銘柄は業績好調な銘柄も多く、初めての決算時に増額修正や事業面での材料が出やすくなる。とくに、IPOまではM&Aなどが自粛・制限されるため、初決算前後で業務提携や資本提携のニュースは出やすい。
また、株価が高ければ「株式分割」などの株主還元策が打たれやすくなる。ただし、この株式分割は曲者だ。1対2の株式分割幅の場合は、上場して最初の分割の場合、分割権利落ち分を埋めきるケースが成長期待の大きい銘柄の場合にはある。ところが、1対3や1対4などの大幅な株式分割の場合は、その後の需給への影響が大きすぎて、株価が分割権利落ち後に低迷が長期化しやすい。
こうした、分割を通過して次は東証1部への市場変更。成長期待の大きい銘柄の場合、1年程度でマザーズや2部から直接1部に市場変更する場合がある。東証1部に市場変更すると次はTOPIX(東証株価指数)組み入れによる買い需要が期待されるために株価は上昇しやすくなる。このように株価上昇のステップアップ材料がIPO銘柄には、明確に存在している。
意外と多い東証1部へのスピード出世
ちなみに、マザーズから東証1部に直接市場変更した銘柄は今年に入り6月までで9銘柄ある。2020年は30銘柄、2019年は24銘柄もある。もちろん、IPOから数年たった銘柄もあるが、いずれも株価は好パフォーマンスが多い。

ただし、2022年4月からは新市場区分(プレミア、スタンダード、グロース)がスタートして、このパターンがどう変化してくるかは、まだ読み切れない。ただ、IPO自体は続くので、市場のステップアップを狙った基本構図に変化はないとみられる。
ソフトバンクはIPOの影
一方、IPOでもっとも警戒する必要があるのは投資ファンドや親会社など株主の事情で、IPO時に公募株式ゼロ、売り出し株のみで出てくる銘柄だ。ファンドの換金目的のIPOとして、初値は公開価格を下回るケースが多い。
最も典型的な例は2018年12月に直接1部にIPOした通信キャリアのソフトバンク(9434)だろう。IPOにあたっての市場からの資金吸収額は2兆6000億円規模の大型上場のケース。さらに、想定価格1500円に対してブックビルディング仮条件は上限も下限も1500円、そうなると公開価格も1500円となる。あまりにも異例な値決めだった。
そして初値は公開価格を約2.4%下回る1463円。問題はその後。上場したソフトバンクの株価が初値1463円を越えるのは2019年7月、公開価格の1500円を越えるのは同じ年の8月。IPO時に買った投資家は半年間も含み益を得られなかった計算になる。
ちなみに、ソフトバンクは配当を実施しているものの、IPO以来株主分割は実施していない。そして、2021年6月末現在、ソフトバンクの上場来高値は2019年の1554円。株価成長がない、キャピタルゲインをほぼ得られていない稀有な銘柄だ。ちなみに、2021年6月末株価は1449円。再びIPO初値を下回る水準に甘んじている。
製造業系、金融系IPOは実は出世株多い
IPOのセカンダリー投資はまだまだ奥が深い。IPO時に社長会見を拒否する企業、メディアを選別する企業の株価は低迷しやすいなどの裏も多い。AIやクラウドなどIT系がIPO人気を席巻してきたが、最近ではIPOも製造業などバリュー的な見方ができる銘柄のパフォーマンスがよくなってきた。
また、証券系・金融系の事業内容を持つIPO銘柄は好パフォーマンスとなりやすく、出世株になりやすい傾向がある。アイ・アールジャパンホールディングス(6035)やマネーフォワード(3994)がその好例だ。IPOセカンダリーでキャピタルゲインを追求してみるのもおもしろい。

